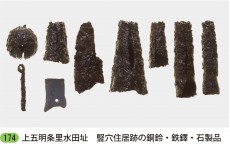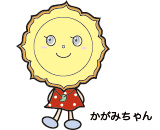書名:北陸新幹線建設事業埋蔵文化財発掘調査報告書7
副書名:沢田鍋土遺跡 立ヶ花表遺跡 立ヶ花城跡
シリーズ番号:94
刊行:2013年(平成25年)3月
沢田鍋土遺跡・立ヶ花表遺跡は中野市高丘丘陵古窯址群の一角にあり、奈良・平安時代の土器生産にかかわる遺構が検出されました。この他、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、中世の遺構と遺物がみつかっています。
立ヶ花表遺跡では、新発見の須恵器窯跡3 基を調査し、焼成部と燃焼部に段差がある特殊な構造の窯跡であることが明らかになりました。特に1 号窯は須恵器大甕を主体的に焼いた窯跡です。
沢田鍋土遺跡では、立ヶ花表遺跡の1 号窯跡と同時期(8 世紀前半)の工人集落の一部を調査しました。工房跡( 竪穴住居跡) は、斜面上方に排水施設と考えられる弧状の溝を廻らせたもので、床下にオンドル状の施設も確認されました。これらの竪穴住居跡より以前の、土師器焼成遺構も確認されており、須恵器・土師器生産に関わる工人集落であったと評価しています。この他、縄文時代・平安時代・中世の粘土採掘跡が見つかっています。
 【遺跡遠景】
【遺跡遠景】
千曲川(信濃川)と篠井川の合流点に望む高丘丘陵の南端部に遺跡があります。左矢印が沢田鍋土遺跡、右矢印が立ヶ花表遺跡の調査地点です。
 【沢田鍋土遺跡:オンドル状施設】
【沢田鍋土遺跡:オンドル状施設】
中央手前のカマド下には、土器で覆ったトンネル状の溝が作られ、暖気が床面を横断する溝をとおって壁際の溝に流れたと推定されます。工房跡(竪穴住居跡)の写真左側は、近代の溝に破壊されています。
 【沢田鍋土遺跡の須恵器1】
【沢田鍋土遺跡の須恵器1】
左が獣脚円面硯の脚部と推定されます。獣脚円面硯の出土例は飯田市恒川遺跡にみられます。
右は杯の底に「井」と刻まれています。沢田鍋土遺跡の北側に、「井」と刻まれた須恵器を多量に焼いた清水山窯跡があります。清水山窯跡では、官衙遺跡などで出土する特殊な器形の須恵器が焼かれています。「井」は奈良・平安時代のこの地域の郡名「高井郡」を示している可能性があります。
 【沢田鍋土遺跡の須恵器2】
【沢田鍋土遺跡の須恵器2】
一般的に須恵器は青灰色の硬質の焼き物(タイプⅠ(写真左側))ですが、沢田鍋土遺跡では、褐色や灰色のやや軟質の須恵器(タイプⅡ・Ⅲ(写真左から2・3番目))も多数出土しました。工人集落であったため、焼き損じを使っていたのかもしれません。
 【沢田鍋土遺跡の円筒形土製品】
【沢田鍋土遺跡の円筒形土製品】
底が無い筒形の土製品です。直径13~16cm程度です。長野県内では、7世紀代と9世紀代に多くみられる遺物とされていますので、長野県内における8世紀代の数少ない出土例であるといえます。カマドの芯材や、土師器焼成遺構にかかわる道具など、その用途には様々な説が出されています。
 【立ヶ花表遺跡出土の須恵器】
【立ヶ花表遺跡出土の須恵器】
立ヶ花表遺跡の窯で焼かれた須恵器です。底部の裏面に、三文字が刻まれています。初めの二文字「多」「井」は判読できますが、三文字目が判読できません。
 【実測図】
【実測図】
上の写真の須恵器の実測図です。























 【中世の掘立柱建物跡】
【中世の掘立柱建物跡】 【礎盤石をもつ柱穴】
【礎盤石をもつ柱穴】 【穴から出土した石臼】
【穴から出土した石臼】 【井戸跡】
【井戸跡】